INTERVIEW
「よりよい未来を、みんなに届ける。」サステナビリティやサーキュラーエコノミーをテーマに、幅広い分野のウェブメディアを運営してきたハーチ株式会社が、創業支援という新たな領域に挑んでいます。東京都のスタートアップ支援事業の一環として始まった「CIRCULAR STARTUP TOKYO」。2024年と2025年に実施された第一期、二期では、広報・コミュニケーション領域のパートナーとして、ひとしずく株式会社が参画しました。サーキュラーエコシステム形成を目指すこの取り組みに、どんな変化がもたらされたのか。実践を振り返りながら、次なるステップへの展望を語っていただきました。
東京都との協働事業としてサーキュラースタートアップの創業支援を実施

ひとしずく担当 ふくもと こうき(以下、ふくもと):
「CIRCULAR STARTUP TOKYO(サーキュラースタートアップ東京)」は2024年に第一期、2025年に第二期を実施し、ひとしずくは一、二期ともにご一緒させていただきました。まずはプログラムについてご紹介いただけますか。
ハーチ株式会社(最高執行責任者)菊池圭介さん(以下、菊池さん):
「サーキュラースタートアップ東京」は、東京都との協働事業です。東京都は2022年に「Global Innovation with STARTUPS」というスタートアップ戦略を掲げ、「10x10x10」、つまり5年間で東京発のユニコーン企業数10倍、東京の起業数10倍、東京都との協働実践数10倍という指標を定めました。その一環で「TOKYO SUTEAM」という支援事業を展開しています。これは東京都が多様な支援者を募集し、協働してスタートアップ支援を展開するもので、協定事業者50社のうちの一社に、ハーチが採択されました。
ほかの49事業者もさまざまなアプローチでスタートアップ支援を行っていますが、僕たちはサーキュラーエコノミーに特化した創業支援を展開しました。サーキュラーエコノミー分野の事業開発に取り組むスタートアップや創業予定の方々に参画いただき、アカデミアや専門家、投資家、企業、業界団体といったこの分野の有識者や第一人者の皆さんにもご協力いただき、新たなエコシステムを創造することを目指しました。プログラム期間中には、サーキュラーエコノミー領域の第一線で活躍する方々や専門家による講義やメンタリングを行い、その他さまざまな企業・団体とも連携しながら、参加者一人ひとりがビジョンやアイデアを磨いてきました。そしてプログラムの集大成として「ファイナルデモデイ」を開催し、参加者のピッチイベント、そして第二期にはサービスや製品の展示も実施しました。

第2期 Final Demo & Exhibition Dayでの展示の様子
ふくもと:
私は広報・PRの仕事を長く続けてきて、ハーチさんというとサステナビリティやサーキュラーエコノミーといったテーマを軸にした“ウェブメディア”という印象が強いんですよね。創業支援事業に取り組まれていると聞いて、幅広く事業を展開されているんだなと興味を惹かれました。どんなきっかけや思いがあったのでしょうか。
菊池さん:
おっしゃる通り僕たちはウェブメディアの運営会社として活動してきて、取材として自治体や教育機関、金融機関などさまざまな分野の専門家の方々にお話をうかがってきました。その中で皆さんがよく口にするのが「今後日本でサーキュラーエコノミーが根づいていくためには、もっと多くの事業家が輩出されて、多様なサービスが生まれ、成長していく必要がある」というご意見でした。この課題に対して、僕たちもメディアとしてできることはなんだろうと考えてきました。自分たちがサービスそのものを生み出すことは今すぐには難しいけれども、サーキュラーエコノミーに関わる事業家や専門家、企業や団体をつないでいくようなエコシステム的な動きはできるんじゃないかなと。折しも投資家の方に「東京都でこんな事業をやるようだよ」と教えていただいたんです。これを機に、スタートアップ支援を起点にして、サーキュラーエコシステムをつくっていこうと考えて協定事業者として名乗りをあげました。
ふくもと:
「サーキュラースタートアップ東京」が初めての取り組みになったんですね。プログラムに参画されたメンターの方々を見ると、多様な分野からの第一人者ばかりで、さすがハーチさんだと。ウェブメディアの運営を通じて信頼関係を築いてきたハーチさんならではの強みだなと思いました。
菊池さん:
もともとは取材や記事執筆依頼などを通じてつながった方ばかりで。皆さん本当にご多忙なのですが、スタートアップ支援の重要性は共通認識として持っているので、ご相談したらぜひ協力しますとご快諾いただきました。それは本当にありがたかったですね。
「広報」を横串に関係性を動かす仕組みを創出
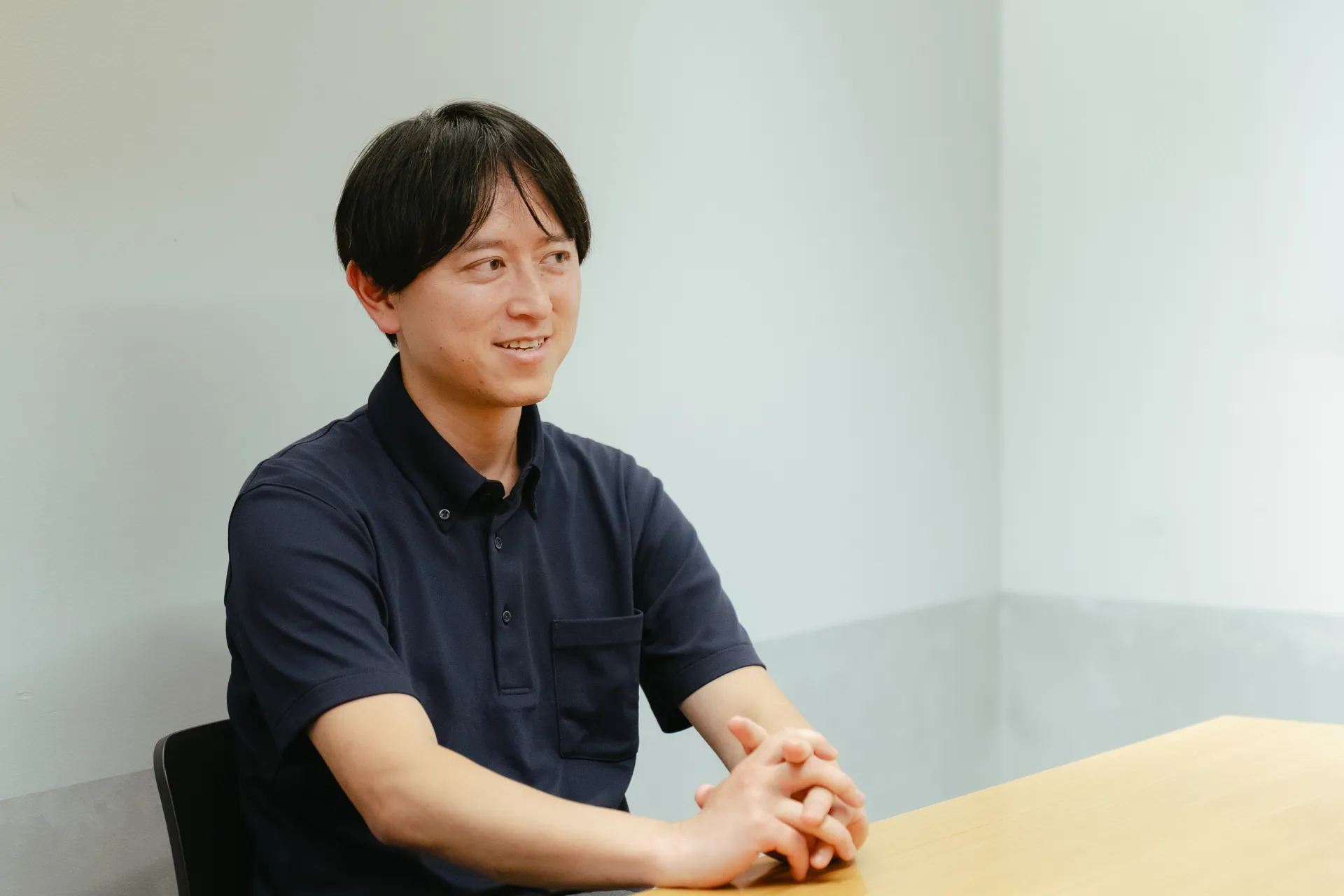
ふくもと:
ひとしずくに声をかけていただいたのは、第一期のデモデイの前でしたよね。
菊池さん:
2024年5月にキックオフイベント、2024年8月に最終のデモデイが予定されていて、ご相談したのは2024年の7月下旬と、だいぶ直前でしたよね(笑)。
ふくもと:
いえいえ(笑)。このタイミングでご相談いただくにあたり、どんな課題があったのでしょうか。
菊池さん:
お声かけした際の要件としては、デモデイへのメディア取材誘致や当日対応でしたよね。ハーチ代表の加藤から「とにかくひとしずくさんには絶対に協力してもらったほうがいい!」と紹介を受けて、とりあえずミーティングを設定させていただきました。ミーティングでは、僕たちがどんなことをやりたいのか、根本のところからお話をして。その中で見えてきた課題として、第二期から意識し始めたのが、デモデイの取材対応など単一の要件だけではなく、「サーキュラースタートアップ東京」というプログラム全体の目的である「サーキュラーエコシステムをつくるにあたって必要なコミュニケーションの構築」でした。
僕たちはウェブメディアですから、活動を発信していくこと自体につまずきを覚えることはありませんでした。でもサーキュラーエコシステムをつくっていくには、情報発信の先にあるコミュニケーションの部分、つまり活動への理解や共感を得て、応援してくれる人、仲間になってくれる人が増えていくような輪の広がりを意識した施策が必要です。コミュニティ運営という面では初めての取り組みだったので、僕たちも何をしたら良くなるのか、模索していたんですね。ひとしずくさんに関わっていただいたことで、第二期からはプログラム参加者の中でのコミュニケーションや、外部も含めて仲間を巻き込んでいくための設計をアドバイスいただけたのは、とてもありがたかったです。
ふくもと:
コミュニティを育てていくには、関係性のデザインが肝になるんですよね。ひとしずくからはいくつかご提案をしました。その一つが「プログラムの参加者みんなが広報する仕組み」です。各社・各人にそれぞれプレスルームをつくってもらって、何か情報発信したり取材を受けたりした際にはそこで参加者コミュニティに対して共有するような仕組みができました。
菊池さん:
プログラム参加者のSlackグループの中で、それぞれがプレスルームというチャンネルを持って投稿してもらうと良い、事務局からはこういう働きかけをするといいですよ、と、ひとしずくさんからアドバイスをいただいて、第二期から実装した施策です。たとえば「こんなニュースリリースを出したら、こういう記事として出ました」という報告を見れば自然に盛り上がりが生まれますし、「なるほど、こういう発信をすることで取り上げてもらえるんだな、じゃあ自分たちももっとやれることがありそうだ」と行動に移してくれる人もいます。この施策のおかげで、コミュニティの中でいい循環が生まれました。
ふくもと:
事務局から、また参加者の皆さんからの発信で記事が出ると、一つひとつメンバーからレスポンスがあって。それをきっかけに参加者同士のコミュニケーションが活性化しているのが見えて、とてもいい雰囲気だなと思いました。参加者コミュニティのコミュニケーション活性化のほか、外部に向けても巻き込む施策もご提案しました。
菊池さん:
はい、第二期には、一般の方にもご覧いただける展示ブースを設けました。第一期はピッチイベントのみの開催で、来場者は基本的には、事業に興味のあるtoBの方だけだったのですが、見て回れるブースを設けたことで、サーキュラーエコノミーに関心のある一般の方もぶらりと寄っていただける雰囲気がつくれました。また、展示ブースがあることで会場内を回遊する余地ができたおかげでしょうか、プログラム参加者、メディア関係者、一般の方のあいだでごく自然にコミュニケーションが発生していたのも良い効果でした。展示を見て「これは面白いですね」と会話が生まれ、名刺交換もごく自然に行われていて。サーキュラーエコノミーという同じ方向性を向いた様々な属性の方同士で柔らかな関わりが生まれていました。関係性の設計ってこういうことなんだな、と、改めてその重要性を実感しました。
ひとしずくさんからアドバイスをいただいて実装した施策を二つお話ししましたが、ほかにもプログラム参加者とのコミュニケーション、プログラムの内容、メディア向けの対応など、あらゆる面でアドバイスをいただきました。それまでサーキュラースタートアップ東京のプロジェクトではそれぞれの機能が分離独立してしまう傾向があったのですが、「広報」の視点で横串を刺すことで、運営プロセスやオペレーションをすべて繋げて考えられるようになったのは大きな変化でしたね。
ふくもと:
私たちからは、ずいぶん細かいこともお伝えしてきましたが、耳を傾けていただいて。リリース1本とっても、第二期は第一期の焼き直しに見えないようにしっかり新しいニュースを伝えるとか、「国内最大級の」と惹きになるフレーズを漏らさずつける、メディアには競合と見られないように「ウェブメディアのハーチ」という文言を変える、デモデイはメディア関係者が集まりやすいように平日開催にするなどなど……。
菊池さん:
ひとしずくさんも一緒に週一回、広報の定例会を設けて、一つひとつ検討してきましたよね。僕たちはウェブメディアとして長く情報発信に携わってきましたが、一言一句、施策の一つひとつが発信した先でどう受け止められ、どう作用するのかをここまで突き詰め、逆算して考え抜いてきたことはなかったように思います。
ふくもと:
PRのプランニングというと、何か大きな企画を提案することのようなイメージがあるかもしれません。でも案外、そういう細かなアクションの積み重ねが重要なんですよね。ハーチさんも忙しい中で、定例で広報ミーティングを設定してくださって。運営プロセス全体を俯瞰で見直しながら、より良い方向に軌道をつくっていく大事な場にすることができたかなと思います。
日本のサーキュラーエコシステムが次なるステージへ進むには有機的な連携構築が課題
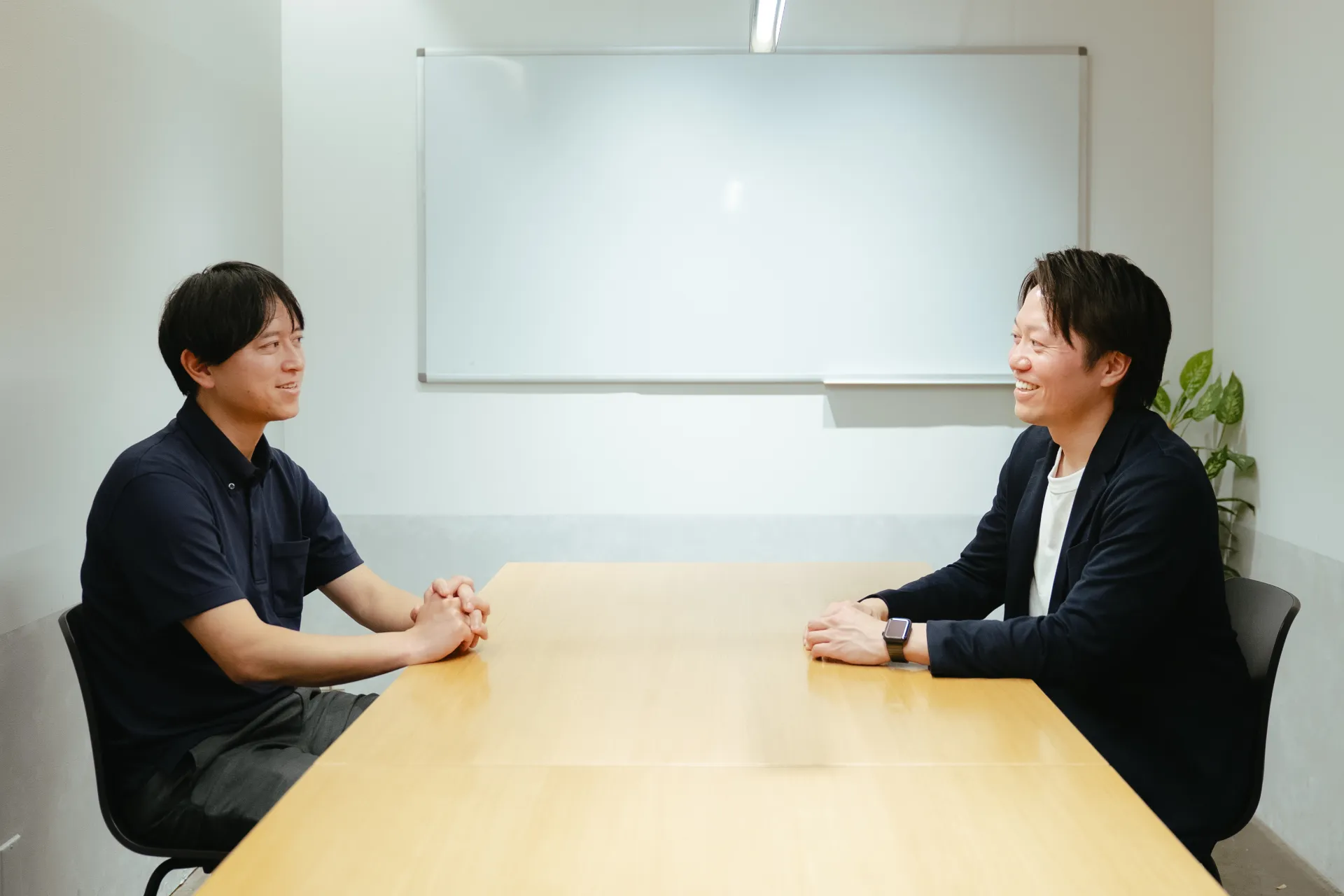
ふくもと:
「サーキュラースタートアップ東京」第二期が無事終了して、振り返りについてもお聞かせいただけますか。プログラム実施にあたっては創業者の数など目標値が定められていたのでしょうか。
菊池さん:
KPIとしては創業数15社、資金調達額1億円、業務提携数5件と定めて運営してきました。結果は資金調達額が9600万円、業務提携数6件と良い数字が達成できたのですが、創業数が4社にとどまってしまい、そこは課題として残りました。とはいえ、起業家からしたら、人生が関わる一大決心です。それに対して、プログラム期間中に起業してほしいなどと踏み込めるものでもないと考えていましたから、僕たちの都合で無理やり強く推し進めることはしませんでした。
ふくもと:
確かにそうですよね。ではプログラム全体を通して、数値目標ではない定性的な面で達成できたこと、また課題として残ったのはどんなことでしょうか。
菊池さん:
第一期、第二期を通じて、横のつながりが醸成されてきたのは、サーキュラーエコシステムをつくるという目的に対して大きな前進になっていますね。それはプログラム参加者同士もさることながら、プログラムに協力いただいたメンター同士にも言えることで。僕は、同じサーキュラーエコノミー領域の中でメンターの方々もつながりを持っているのかなと想像していたのですが、案外「オンラインでは面識があるけれど直接会うのは初めて」という方もいらっしゃいました。創業支援をハブにして、こうしてサーキュラーエコノミーに関わる人たちが集まり、直接つながり合える場をつくることができたのは、ひとつ貢献できたところではないかと考えています。
一方で振り返ってみると、僕たちの役割としては、そうやってできたつながりを、もっと有機的な結びつきにする取り組みをするべきだったのではないかと思う面もあります。「サーキュラースタートアップ東京」というプログラムを一つ形にすることができて、参加者にも満足していただき、創業したスタートアップも成長の兆しを力強く見せてくれたわけですが、たとえて言うなら竹の子のように一社一社がそれぞれの力でまっすぐに成長していったんですね。もちろん、それ自体は価値ある成果でしたが、サーキュラーエコシステムを構築する上では、それぞれの領域や事業のフェーズを俯瞰して次のさらに大きなビジョンを示しながら、一社一社を有機的につなぐことも必要なのではないかと思うんです。これは僕たちにとっての課題ですね。
ふくもと:
プログラムに参加した16チームとの連携はこれからも続いていくんですよね。
菊池さん:
そうですね。Slackコミュニティは継続していて、その中で今もコミュニケーションは取っています。また「TOKYO SUTEAM」のほかの協定事業者と合同でイベントを開催する際にも声をかけたり、ハーチが運営する「サーキュラーエコノミーハブ」で第二期生を取材したりと、何かと関わりは続いています。
未来を見据えて、サーキュラーエコシステム支援を深化・拡張
ふくもと:
今後の展望についてもお聞かせください。今後も日本のサーキュラーエコシステムを活性化していくために、私たちひとしずくもハーチさんと連携しながら取り組みを続けていきたいと思っています。
菊池さん:
こちらこそ、ぜひよろしくお願いします!これからは「サーキュラースタートアップ東京」の枠組みを横展開していきたいと考えています。ハーチの事業はウェブメディアが主軸ではありますが、そこから派生してスクールプログラムやコミュニティ形成といった新しい軸も育ちつつあります。そこではやはり参加者同士や外部に対するコミュニケーションが非常に大事になってくるので、そういった部分でも今後、ひとしずくさんと一緒にお仕事したいですね。
ふくもと:
ハーチさんだったら、メンターや講師陣も第一線の方々が協力を快諾してくださるでしょうね。これまでのウェブメディアとして、また「サーキュラースタートアップ東京」の実績はほかにはない強みだと思います。
菊池さん:
ありがとうございます。スクールプログラムについても、「サーキュラースタートアップ東京」の運営経験を経て幅を広げられそうだなと。これまでは、大企業や自治体に向けたサステナビリティやサーキュラーエコノミーに関する研修プログラムが主だったのですが、さらに資金調達や会計なども、創業支援の観点からのコンテンツとして展開できそうだと考えているところです。これらの領域については、専門性を持つパートナーとも連携しながら、それぞれの強みを生かした協働の形を目指したいと思っています。
ふくもと:
まだ具体的には考えていないけれどいずれは、と考えているサーキュラースタートアップ予備軍の方々に働きかけるのも、未来をつなげていくという意味では重要ですよね。
菊池さん:
おっしゃる通りです。今まさに創業に向けてがんばっている人、これからという人、今は大企業で働いているけれど興味はあるという人、第一線で活躍する専門家の皆さん、様々な立場やフェーズにある人々を有機的につないで、日本のサーキュラーエコシステムを活性化していく。これを目標にこれからもチャレンジしていきたいと考えています。
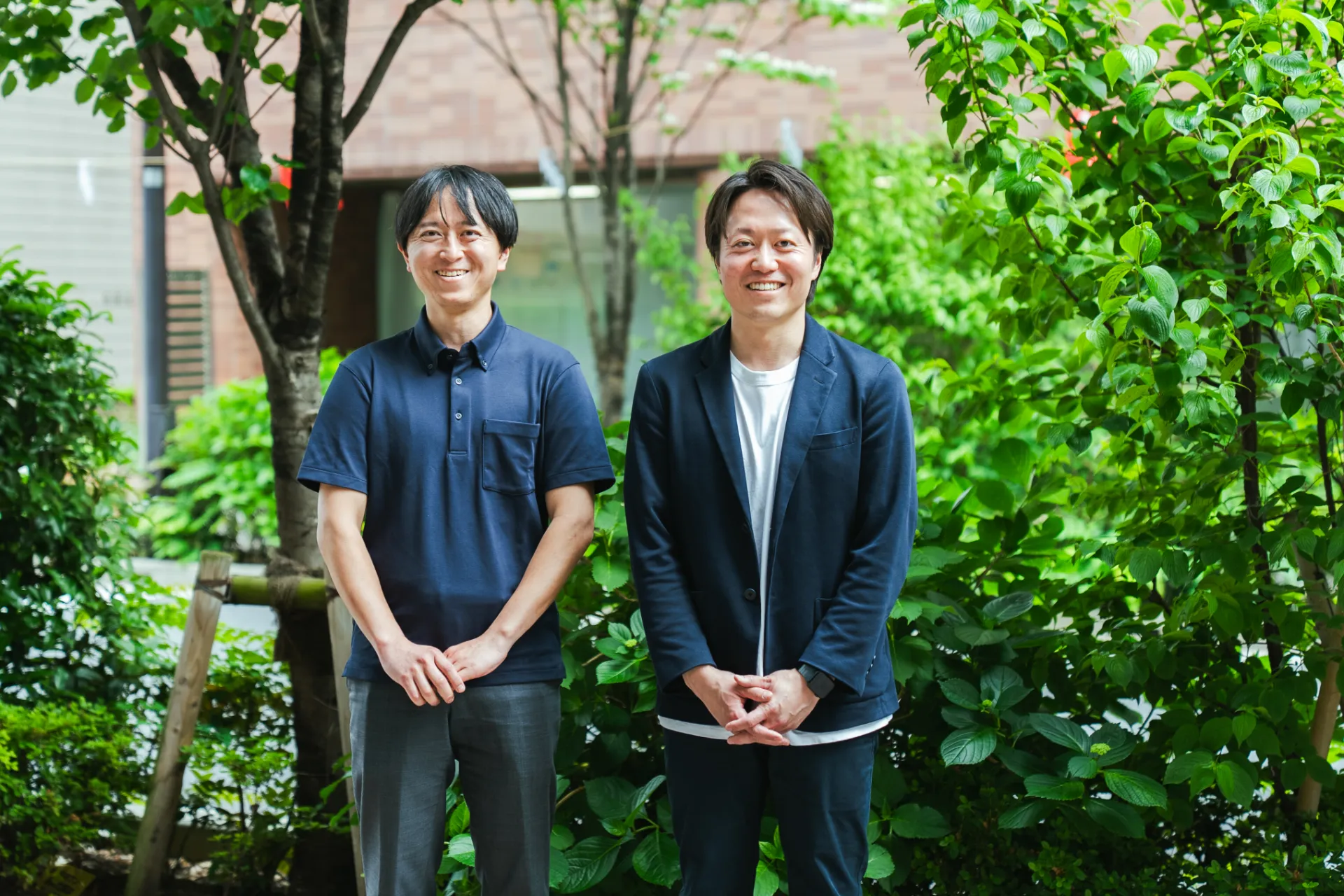
撮影:ほりごめ ひろゆき 編集:いとう ひろこ
Director: ふくもとこうき

